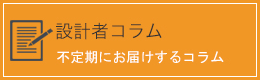設計者コラム
#106 光学系の環境温度評価
光学系の設計は通常、使用環境温度が20°前後が前提となることが多いかと思います。
車載用の光学系になると、これが氷点下から数十度に渡る範囲で光学性能を保証しなくてはならないケースが多々あります。
環境温度が変わると硝材の屈折率、レンズの曲率半径や厚み、非球面係数などが変化を受けて変動します。
またレンズを保持しているレンズ枠も素材の線膨張係数に従って膨張・収縮しますので、レンズ間隔も変動します。
こういった温度変化時の光学性能の検証をZemaxで行うには通常、環境温度を変えたマルチコンフィグレーションを使用します。
マルチコンフィグレーションエディタには"熱解析の設定"というボタンがあります。
このボタンを押すと、
・コンフィグレーション数
・最低温度
・最高温度
の入力項目があり、最低温度から最高温度の範囲を指定したコンフィグレーション数で温度分割したコンフィグレーションが自動生成されます。
各温度のマルチコンフィグレーションでは、上述のようなパラメータが各設定温度で自動的に変動計算された状態になります。
解析を行いたい温度コンフィグレーションに移動して、収差図やMTFなどを解析すれば目的は達成されます。
またこの状態で適切なメリットファンクションを設定した後、最適化を行えば温度変化に強い光学系の設計が可能になります。
しかし実際には、そのままで意図するような最適化は困難で、温度変化に強い硝材の選択などが必須になります。
ほぼ同じ機能はOpTaliXにも搭載されています。
環境温度変化を考えなくてはならない光学系を検証したい方は試してみて下さい。